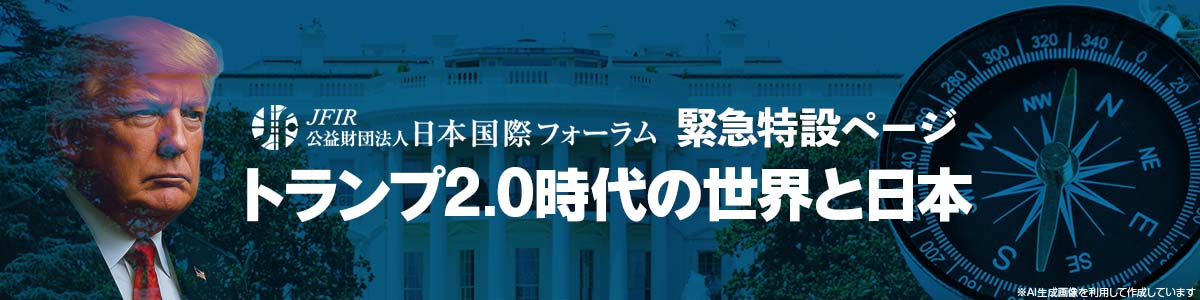JFIR research studies
JFIR seminar / symposium
欧州は今:重層的多極化する欧州とアジア
現在、業務の都合上お電話での対応が難しくなっております。
お問合せ等はお電話ではなく代表メール( jfir@jfir.or.jp )にお送りいただくか
「お問合せ」欄よりお願い致します。
最新のコメンタリー
バックナンバー
e-論壇百花斉放
JFIR主催 / GFJ連携 / CEAC連携 / WSD後援
分断世界とカーニー演説の価値─長期戦略への羅針盤
勢力圏抗争に、本格的に舵を切った米大統領トランプ。年明け早々のベネズエラへの軍事作戦行動に続いて、かねて意欲を示してきたデンマーク自治領グリーンランドの領有に向けて野望をむき出しにした。「戦後秩序の砦(とりで)」北大西洋条約機構(NATO)に亀裂を生じさせかねないトランプの専横極まりない振舞い。米欧間に緊張が走った。最も敏感に、研ぎ澄まされた反応で自国のポジションを鮮明にしたのが、隣国カナダだっ
鈴木 美勝
日本国際フォーラム上席研究員「共産党独裁」は衰退し消滅へ
近年、日本共産党は「自由な共産主義」について、オンラインや赤旗で主として青年、学生、労働者、民青同盟員、青年党員らに対しキャンペーンを展開している。これは旧ソ連や中国の例から「共産主義には自由がない」との「反共攻撃」を打ち砕き、若い層を中心に党勢拡大を図る狙いがある。なぜなら、共産党はこのような「反共攻撃」が党勢後退の最大の要因と考えているからである(赤旗2024年6月12日)。そこで、志位和夫
加藤 成一
外交評論家(元弁護士)日本国を守る強力な「敵基地攻撃能力」保有
高市内閣は、国民の生命と財産を守るため、日本の防衛政策の基本を定める「安保3文書」の改定や防衛費の増額をはじめ、防衛力の抜本的強化に取り組んでいる。核を放棄しない北朝鮮や、核戦力を含む軍備増強を急速に進める中国の脅威、台湾有事・尖閣有事の危険性などを考えれば、日本にとって他国からのミサイル攻撃を抑止するため、他国の領域にあるミサイル発射基地などを攻撃する能力である「敵基地攻撃能力」の保有は日本防
加藤 成一
外交評論家(元弁護士)新テーマに、AIと安全保障および人道問題が関連した案件はどうか?
去る1月20日に開催された『公開シンポジウム:多極秩序の狭間で:日本外交と「狭間国家」の生存戦略』にて、当フォーラムが今後取り組むべきテーマについてのアンケートがあった。その返信に私が記したテーマよりも、拙先稿で議論したAIと安全保障および人道問題に関連したテーマの方が日本のグローバル政策に意味がありそうだと思えてきた。先稿では英王室国際問題研究所上級相談役フェローのリチャード・バロンズ元英陸軍
河村 英太崚
外交評論家中国こそ現代の「軍国主義」だ
2025年11月7日の衆議院予算委員会での「台湾有事は集団的自衛権行使の存立危機事態となり得る」との高市首相発言に対して中国は激しく反発し、対日渡航の大幅制限、自衛隊機に対する危険なレーダー照射、レアアース輸出規制、パンダ回収、対外悪宣伝活動など、様々な報復措置を取り、2026年2月8日の総選挙で高市自民党が圧勝した現在でも「高市発言」の撤回を執拗に要求している。しかし、安保法制における集団的自
加藤 成一
外交評論家(元弁護士)「高市防衛力強化」がなぜ戦争国家なのか?
高市自民党は2026年2月8日の総選挙で198議席から単独過半数を超える316議席を獲得し圧勝した。これに対し中道改革連合は167議席から49議席に激減し惨敗した。この劇的な選挙結果を受けて高市首相は、選挙公約である「責任ある積極財政」と「防衛力の抜本的強化」の推進を宣言した。 中道改革連合の野田共同代表や各候補者らは選挙期間中、高市首相公約の「防衛力の抜本的強化」に反対し、「高市政権
加藤 成一
外交評論家(元弁護士)最近の活動報告
バックナンバー
日本国際フォーラム ( JFIR ) とは
日本国際フォーラムは、市民社会の側から、つまり民間・非営利・独立・超党派の立場から、会員および市民の参加を得て、外交・国際問題について研究・討論・交流・提言等の活動を促し、もって内外の世論の啓発に努めることを目的としますが、それ自体が組織として特定の政策上の立場を支持し、もしくは排斥することはありません。
特定の提言の内容について責任を有するのは、あくまでもその提言に署名した者に限られます。日本国際フォーラムは、1987年3月に財団法人として設立されましたが、2011年4月以降は、内閣総理大臣からその活動の公益性を認められて、公益財団法人に移行しました。