メモ
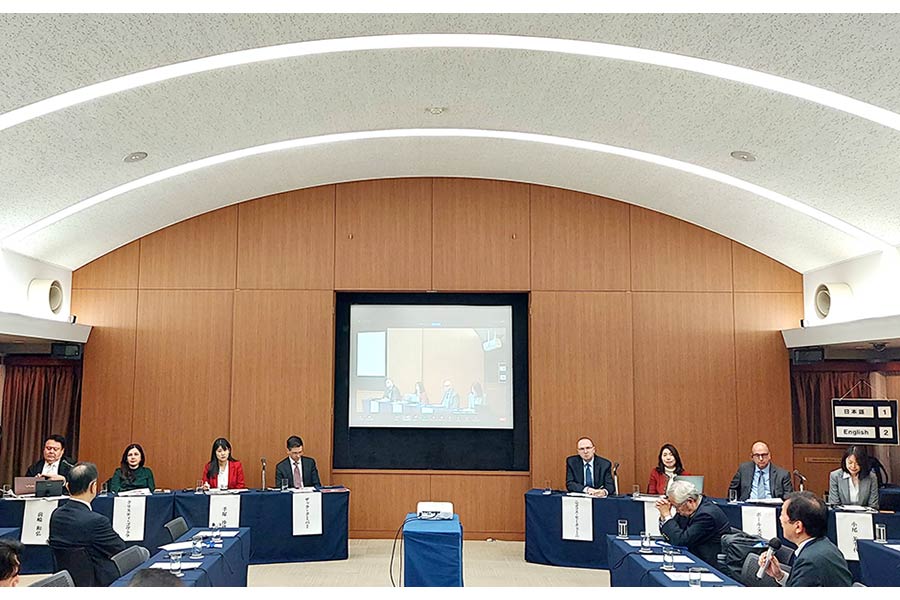
標記国際シンポジウムが、下記1.~4.の日時、場所、参加者にて開催されたところ、その議事概要は下記5.のとおり。
記
1.日 時:2024年11月18日 (月) 14:00-16:00
2.会 場:国際文化会館(ZOOMウェビナーとのハイブリッド開催)
3.参加者:165名
4.登壇者:(プログラム登場順)
【日本側】前嶋 和弘 上智大学教授
渡辺 まゆ JFIR代表理事・理事長
鈴木 一敏 上智大学教授
手塚 沙織 南山大学准教授
三牧 聖子 同志社大学准教授
小尾 美千代 南山大学教授
【米国側】クリスティ・ゴヴェラ オックスフォード大学准教授
ザック・クーパー アメリカン・エンタープライズ研究所(AEI)シニアフェロー
ニコラス・セーチェニ 戦略国際問題研究所(CSIS)日本部上席研究員/
地政学・外交政策副部長
ポール・スラシック ヤングスタウン州立大学教授/ハドソン研究所 非常勤フェロー
5.議事概要:
渡辺理事長より開幕挨拶が行われた後、前嶋和弘主査の司会の下、2つのセッションにて日米メンバーより報告がなされた。その概要は以下の通り。
<セッション1「経済・貿易・人の移動をめぐる日米の課題」>
(1)ゴヴェラメンバー
近年、新型コロナウイルスの世界的流行、経済的強制(威圧)の増加、ウクライナ戦争などを契機に、日米を含む世界中で経済安全保障への注目が高まっている。対応するために国内外の政策ツールが急速に開発されるも、経済安全保障の定義をめぐるコンセンサスがない。経済安全保障には、3つの重なり合う動機付けがある。一つは強靭性(Resilience)、介入/干渉リスクの低減である。二つ目が競争力(Competitiveness)で、国内の経済力を積極的に促すためのステップをとることである。三つめが保護(Protection)であり、海外からの競争制限や不利な競争から守ることである。
この3点に基づいて日米の取り組みを比較すると、日本は世界初の経済安全保障に関する法律を制定している。日米共通の取り組みとしては、半導体・クリーンエネルギーへの補助金給付による企業支援、競争力の回復を図る他、サプライチェーンの強靭性や対内投資のスクリーニング審査を強化している。日本にはない取り組みとして、米国は技術輸出規制など対外投資のスクリーニングを実施するほか、232条、301条関税などの措置をとっている。このように、「強靭性」「競争力」「保護」を様々に組み合わせて政策ツールが作られているが、第三者からの保護のために用いるのか、日米が互いに対抗するために用いられるのかによって、その意味は異なってくる。
日米は経済安全保障において経済版2+2、日米商務・産業パートナーシップ(JUCIP)等の二国間枠組に加えて、Quadやインド太平洋経済枠組み(IPEF)、鉱物安全保障パートナーシップ(MSP)等の多国間枠組みにおいても、中核をなしている。「強靭性」を促進し、特にサプライチェーンや重要な新興技術、標準における「競争力」を高めるという、深い目標を共有している。
しかし、日米で新政権が発足し、経済安全保障が今後どうなるのかについて多くの疑問が生まれている。協力には、「懸念(concerns)」の共有と「利益(interests)」の共有という2つの原動力(drivers)があるが、前者について、日米は多くの共通点がある。例えば、世論調査によれば、両国ともアジアにおける中国の影響力を懸念する声が多く、日米同盟への支持は強い。
経済安全保障の強化に対する解決策は一つではない。何を事実と捉え、どのような影響が及ぶのかについての意見が分かれることもあり、摂った政策によっては日米間に緊張を生みかねない。日米協力は数多くの多国間枠組みに組み込まれていることから、米国のリーダーシップの後退や、政策の変化が懸念される場合は、より大きな枠組みに協力関係を組み込むようにするとよいだろう。
(2)鈴木メンバー
権威主義国が威圧的になりつつある今、日米同盟は基軸であり死活的に重要だが、軍事面だけではなく、非軍事分野も含めた日米の協力関係全体が重要になっている。
その理由は2つある。一つは同盟の信憑性である。同盟は「守られない」という疑念が生じると抑止が効かなくなる。反対に、同盟国間で利害が共有される、価値観が共有されているなど、「あの国々は特別いい関係だ」と、外から見えるということが、相手のパーセプションに影響し、同盟の信憑性が高まる。
二つ目は、経済と政治の再統合である。90年代、00年代のグローバル化の時代には、相手との政治的な関係をあまり考慮せずビジネスをする傾向が強かったが、特に2010年代に入ってからは、地政学的なグループに沿って経済関係を考える傾向が強まった。冷戦期と違ってライバル国との間に貿易依存度も上がり、サプライチェーンも伸びたため、依存関係を利用して外国に圧力をかけるということが増えた。そうなると、直接投資が大きい産業や技術にかかわる産業では特に、敵対国を避ける傾向が生まれ、結果として、友好国で協力する必要が高まった。
このように、米中対立の文脈においても非常に重要な日米協力だが、米国はWTOには距離を置き、FTAもNAFTAの改定のみであるし、日米貿易協定も正式にFTAと呼べるかは微妙なものであり、TPPは脱退、IPEFも貿易自由化はしないなど、消極的な姿勢をとっている。一般的に自由化は利益が大きく、損失の少ない分野から始めるが、その範囲をある程度以上拡大すると、反対者が増え、組織化や動員されることで政治的な力を持つようになる。反対が出てきた時点で無理してでも自由化を進めると、国内産業は対応せざるを得ず、徐々に反対の声が減っていくが、反対に一度保護すると、陳情すれば保護してもらえるという成功体験になっていまい、組織が強くなり政治活動がしやすくなり、抵抗勢力として残る。こうした難しい産業の例が、日本では農業であり、今の日米関係なら、米国の場合は鉄鋼や自動車である。このような難しい産業でお互いに折り合えずにもめると、同盟や経済安全保障のための協力関係を弱めてしまうリスクがある。
それでは日米協力を進めるにはどうすべきか。部分的に参考になりそうなのが、日本のFTA交渉の取り組みである。日本政府は農業と工業を分離する交渉戦術を巧みに使いながら、農業という難しい産業の自由化を避けつつ、多くのFTAを成立させた。第一期トランプ政権で締結された日米貿易協定においても、日本の農業と米国の自動車を事実上除外し、トップに問題が上がり政治問題化されないように実務的に処理するなどの手法をとっている。第二期トランプ政権の四年間では、対外的に難しい問題はお互いに避け、できるところでできる限りの協力をし、形を整えて、それを思い切りアピールするというのが現実的な対処法の一つではないか。もちろん、長期的にはこうした難しい問題にそれぞれが国内で対処することが必要だ。
(3)クーパーメンバー
貿易・経済問題は日米間の協力分野であったが、今後四年間は摩擦分野になるだろう。そこで、①トランプ政権がなぜ保護主義に傾きつつあるのか、②それが特に貿易にとって何を意味するのか、③日米はどのように協力して取り組むことができるのか、について説明したい。
まず①について、トランプ氏や彼に近い人からよくきかれるのが、以下の5つの主張である。1)保護主義的な政策の強化により、米国内での製造業の復活を早めることができる。トランプ氏は、製造業が経済の中核にあると考えている。2)より保護主義的な政策が貿易赤字の削減につながると考えている。トランプ氏は貿易赤字を、輸出よりも輸入が多い国の損失と見なしている。3)関税を通じて米国の歳入を増やしたい。米国の所得税全体を関税に置き換えたいとも発言している。4)保護主義をある特定の方法で適用すれば、米国の競争力を敵対国に対して高められる。例えば、中国による米国の資本市場や技術へのアクセスの制限により、長期的には米国が有利になる可能性がある。5)米国による海外からの製品購入を減らすこと。この声は残念ながら潜在的な敵対国のみならず、日本のような同盟国やパートナーからもある。
こうした主張を踏まえて、トランプ政権が早い段階で実行に移すと思われる5つの政策は以下の通りである。1)トランプ氏はTPPから離脱したように、IPEFから離脱する可能性が高い。ただし、ゴヴェラメンバーの報告にあったIPEFの「強靭性」の側面、サプライチェーンの部分はトランプ政権でも支持される可能性がある。2)世界的な関税の適用であり、トランプ氏は最大20%の関税をかけると明言しており、特に米国と自由貿易協定を締結する同盟国にとっては非常に問題である。3)中国に対しては、30~40%という高い関税をまもなく導入するだろう。トランプ氏は、最終的に60%にまで引き上げると発言しているが、短期的には30~40%が現実的だろう。4)米国はWTOの上級委員会の委員の選任に引き続き反対するだろう。5)米国のCPTPPへの復帰への望みにとどめを刺すだろう。かつては共和党が自由貿易を比較的重視し、民主党はそうでもないとみられていたが、現在は両党とも保護主義的なスタンスである。米国の貿易への姿勢を端的に説明しているは、第一期トランプ政権でアドバイザーを務めた人物の一言だ;「我々は既存のシステムを利用して他者の行動を変えようとしているのではない。既存のシステムを壊そうとしているのだ」。残念ながら、今後、日米関係は極めて困難な環境におかれることになるだろう。
それではどうすればよいのか。米国では貿易や経済的アプローチについて、よく「促進」と「保護」という2つの側面から語る。この点について、実は日米は互いに共有できる専門知識を多く有している。米国は輸出管理・規制分野での経験や知識は世界トップである。他方、産業政策推進のための政府政策の活用についてはさほど専門的な知識はないが、この分野では日本が何十年もの間、世界をリードしている。現在の貿易・経済環境において、新しい活路を見出すにあたり、日米両国は互いに学び合うことができるだろう。
(4)手塚メンバー
国際移動の観点から、日米の協力のあり方について見ていく。まず、両国の課題について見ると、米国は移民国家であり、毎年約100万人の移民を受け入れている。一方で、日本は公式には移民を受け入れておらず、ここで既に日米間の構造的な違いがある。
日米における越境者をめぐり、両国の越境者のステータスを「帰化(外国生まれの市民)」、「移民(永住権獲得)」、「難民・庇護申請」、「非正規」に分けて、それぞれについて両国が直面する課題の本質を、「narrative」「change/probability」「relationship」に分類して見てみると、以下のことが見て取れる。
一つは、米国における「帰化(外国生まれの市民)」に分類される、つまり帰化した者(外国生まれの市民)の数は2010年から2020年の各年平均は72万人、2022年にはおよそ97万人であり、数万人単位で勝敗が決まる大統領選に大きな変化をもたらしている。この分類で大きなグループを形成するヒスパニック系の投票者が、民主党の支持基盤の一つでもあったとされるが、2024年度の大統領選にてトランプ支持に回ったことがトランプ氏勝利の要因の一つと言われている。ヒスパニック系人口はethnic groupの中で最も増加が大きく、この増加が政治情勢をどのように変化させるのかが、今後のアメリカ政治の注目点である。
「移民(永住権獲得)」をめぐっては、受入国への経済的貢献の度合いによって、高度・中程度人材と定義され、彼らによる人口動態、文化、社会の変化が政府の取り組むべき課題を生み出すであろう。
次に、「難民・庇護申請」、「非正規」について見ると、米国では1100万人以上の非正規移民が存在すると言われている。法治国家において正式な滞在許可がない者(非正規移民)への警戒感と、受入国にどれほどの財政的な負担がかかるのかという懸念を受入国は抱く。トランプ氏は任期中に非正規移民の強制送還を実行すると豪語するが、莫大な費用がかかる。また別の問題として、強制送還の結果としての労働者減少によるインフレも懸念されている。一方日本では、技能実習生の行方不明者が1万人に達しようとしているが、彼らが消息不明となるといずれビザが失効し、不法滞在者、不法移民となる。人手不足を背景とした一時的な労働力を輸入するゲストワーカープログラムをどのような形で開始・運営・廃止していくのかが、将来的に非正規移民を生み出すかどうかを左右する。
ゲストワーカープログラムの構造的問題は、完全に相反するインセンティブが2つあることである。政策立案者はプログラムを一時的なものとして構築するにもかかわらず、一定期間が経つと、雇用主と外国人労働者に経路依存性が生まれる。雇用者は安い賃金で雇うことができ、労働者は母国との賃金格差から、母国で働くよりも多く稼ぐことができ、その送金に母国の家族が頼る状況が続くため、契約終了後も働き続けるインセンティブが生まれ、非正規滞在者を生み出す構造は解消されない。
民族や人種の異なる人々をどのように定義するのか、その人々がどのくらいの規模で存在し、それにより受入国がどのように変化するのか、その変化に対してどのような関係を構築していくのか、という点を見ていくことが重要である。
【質疑応答】
Q1.トランプ氏の台湾有事への対応
A1. トランプ氏の対応は予測が難しく、彼自身が明確なビジョンを持ってこうした状況に対峙すると考えられないため、提示された選択肢から選ぶだけになるのではないか。ただ、トランプ氏の安全保障チームは台湾支持を主張し、経済チームは米中経済関係を重視するため、この二者の間で緊張が生じると予想される(クーパーメンバー)。
Q2. IPEFの維持可能性とIPEFにおける日本の役割
A2. 日本がTPPと同様にIPEFを救うことは難しいだろう。IPEFの柱の一つのサプライチェーンへの米国の取り組みを支えることはあっても、この地域の多くの国がIPEFに失望するなか、日本がIPEFの存続に必要な政治的資本の全てを注ぎ込むインセンティブがあるとは考えられない。安倍元首相にはCPTPPを成功させるたけの政治的資本と国際的地位があったが、日本の政治が難しい現在、日本の指導者が同等の時間と労力をかけられるとは思えない(クーパーメンバー)。
Q3. 民主党の関税政策と労働者層への対応
A3. 民主党内では労働者階級の経済的懸念に対処しなかったために選挙に負けたという思いがある。トランプ氏が労働者階級の懸念に対応しているとは言えないが、多くの人々がそう感じているのが現状である。民主党はトランプ氏の経済政策を一部採用すべきと考えるようになっているが、それが最終的に機能する可能性が高いわけでもない(クーパーメンバー)。
トランプ政権とバイデン政権には多くの経済政策における継続性があるといえる。バイデン政権による対中関税政策の多くが、トランプ政権でも継続されている。他方、バイデン政権は自由貿易や他国への市場アクセスの提供への取り組みがなかったが、第二期トランプ政権では関税などの面でより過激になることが予想される(ゴヴェラメンバー)。
<セッション2「気候変動・社会的分断・民主主義のあり方をめぐる日米の課題」>
(1)セーチェーニメンバー
米国大統領選挙の結果をみると、米国国民は米国が誤った方向に進んでいると感じて変化を望み、トランプ氏がその実現にベストな候補者だと考えたのだろう。10月25日実施のNY Times紙とシエナ・カレッジによる世論調査によると、回答者の過半数(51%)が米国の政治システムと経済構造に大きな変化が必要だと回答し、その内訳は共和党員56%、民主党員48%、無党派層47%であった。また、回答者の62%が「政府は主として自らとエリート層のために働いている」と回答し、その内訳は共和党員77%、無所属66%、民主党員33%であった。一方、「政府は主として国民や国のために働いている」との回答は33%に過ぎず、その内訳は民主党員53%、共和党員20%、無所属28%であった。トランプ支持者はトランプ氏が経済を改善し、官僚エリートを一掃することで政府をより効率的なものにすることを期待する。一方トランプ氏を批判する人々は、その関税政策が経済に打撃を与え、公務員がトランプ氏の忠実な支持者に置き換わることで、公務員が立場を悪用し、政敵に復讐することを恐れている。トランプ政権の誕生は米国の民主主義の将来に大きな不安を生み出すだろうが、民主主義を維持する役割を担う諸機関のレジリエンスを信じている。
日本の政治に目を転じると、日本国民も先日の衆議院選挙で国内政治の現状に審判を下し、裏金問題への対応の甘さに対する不満を背景に、連立政党に罰を与えた。日米の2つの選挙には、興味深い類似点がある。日本の有権者は政治や経済政策に変化を求めているようにみえるが、このことは、自民党が政治資金の使途をめぐる制度改革を実施し、有権者の信頼を取り戻そうとする一方で、税制改革で野党と交渉する姿に表れている。日本の民主主義の健全性には疑いの余地はないが、政治の不安定な状態が長期化すれば、米国内では、日本における大胆な外交・安全保障政策を実施し、国際舞台で重要な発言力を維持する能力に懸念が生じる可能性がある。
日米の政治的な変化は日米関係にどのような意味をもたらすのか。第一期トランプ政権における日米同盟をめぐる動きを振り返ると、第一に、同政権は日本の防衛力強化と中国抑止への決意に鼓舞された。第二に、同政権は地域外交の枠組みとして、「自由で開かれたインド太平洋」という日本の構想を受け入れた。第三に、いわゆる「ミニ・ラテラリズム」として、Quadの下での日米豪印の協調を取り入れた。第四に、安倍晋三元首相のリーダーシップに依るところ大きいだろうが、第一期トランプ政権で日米は戦略を一致させた。
日本は選挙中のトランプ氏の過激な発言から、トランプ政権下でのディール外交や同盟関係への懐疑的な見方を懸念しているかもしれない。しかし、トランプ氏は日本を、中国に対峙する強い国であり信頼できる同盟国として肯定的に捉えていると考える。アジアや世界の安定と繁栄を脅かす独裁国家がもたらす課題に立ち向かうためには、日米両国は、QuadやG7といった公式・非公式な枠組に関係なく、志を同じくする民主主義国家と緊密に連携するしか選択肢がないのが現実だ。
本日のシンポジウムのテーマ「分断の時代」は、両国における政治環境の対立を反映しているかもしれないが、日米関係には当てはまらない。政治の移行期には常に不確実性が伴うが、日米同盟は両国首脳が基盤を強化し、今後も継続するものと確信している。
(2)三牧メンバー
民主党のハリス候補が敗北した原因には複数の要因が絡んでおり、その一つが性別と人種である。特に、Z世代(1980年代後半から2010年代前半に生まれた世代)の民主党の支持率が前回よりも低下し、同世代におけるジェンダーの分断が顕著となった。民主党が若年層男性にリーチできなかったのは戦略的な問題なのか根本的な問題なのかが分析されている。
さらに、パレスチナ自治区ガザでの情勢もとりわけアラブ系市民の多いミシガン州に影響があった。民主党支持層ではイスラエルの軍事行動をめぐり分断があった。若年層の民主党支持者がイスラエルの軍事行動に批判的で、民主党内での支持固めに苦戦した。また、中絶の権利を争点にしようとしたハリス候補であったが、特に中絶に関心を持つはずの若年層をそれほど引き付けることにならず、むしろ男性票を遠ざける結果となった。中絶の権利や民主主義を強調した民主党の戦略は、経済や移民問題が主要な争点となる中で、選挙戦そのものが、人々の求めていたものかみ合っていなかったのではないかという分析がなされている。
世界的な傾向の中に米国大統領選挙を位置付けてみると何が見えるか。トランプ氏は前の任期で経済問題において自らを「変化の候補者」として位置づけることができたため勝利した。今回の出口調査によると、少なくとも70%の国民が現在の政治や経済の方向性に不満を持っていた。既存の秩序や政治に不満があるなかで行われた選挙では、伝統的な手法からかけ離れたトランプ氏の手法が米国市民の視点とかみ合った。バイデン大統領は政治のインサイダーとしての印象が強く、ハリス候補もより変化を打ち出す可能性があったものの、バイデン政権の路線を継承する立場を打ち出したことで、変化の候補として人々に認識されてもらうことに失敗した。
世界に目を転じると、米国だけでなく、イギリス、フランス、インド、韓国などでも既存の政治秩序に対する不信や不満が蓄積し、それが野党への怒りという形で様々な政治変動が起きているといえる。インドではモディ首相が連立政権を組むことを余儀なくされ、イギリスでは労働党が勝利し保守党政権に変わった。韓国でも野党が総選挙で地滑り的な勝利をおさめ、フランスでも右派の国民連合が躍進した。日本でも、衆議院選挙で自民党が議会の過半数の議席を失った。数年前までは国内外の識者が日本を「ポピュリズムがない国」と特徴づけていたが、衆議院選挙のみならず、東京都知事選挙や兵庫県知事選挙の結果を見ると、エスタブリッシュメントに対する不満・不信がポピュリスト運動を起こしているのではないか。今後の民主主義への挑戦として、ポピュリズムの台頭が日米の大きな課題となるのではないか。
(3)スラシックメンバー
日米関係の問題はある意味で社会的分断という文脈における民主主義の産物といえる。米国政治では「2つのアメリカ」という表現がよく用いられるが、この表現は、公民権運動を主導したキング牧師が米国における人種平等の欠如を指摘する際に用いられたのが最初である。その後、2004年に副大統領候補となったジョン・エドワーズ氏が選挙演説でこの表現を再び用いたが、エドワーズ氏にとってこの表現は人種問題だけではなく経済的不平等に焦点を当てたものであり、医療制度や教育制度の改善を目的とした政府プログラムの拡充を訴えた。
「2つのアメリカ」を社会階級の視点からみると、米国では「労働者階級」は大学の学位を持たない人々と定義され、さらに人種や民族で区分することもある。
歴史的に、民主党は労働者階級を代表する政党であり、労働組合や団体交渉の権利を支持することで彼らの忠誠を得てきた。ところが、2016年、新たな「2つのアメリカ」が登場した。トランプ氏は特に白人の労働者階級の有権者から支持を得て、現在では労働者階級の有権者が共和党員になるという米国政治の再編が起きた。トランプ氏は経済的に取り残された人々を支援するための政府プログラムに焦点を当てるのではなく、輸入が雇用を奪い、気候変動対策が労働者階級の仕事を奪うと主張し、民主党が過去に行った関税で輸入を制限するような保護主義は効果がなかったと批判した。
同じく2016年、J.D.ヴァンスはオハイオ州ミドルタウンの労働者階級出身としてその苦境を描いた『Hillbilly Elegy』を出版した。書籍ではヴァンス氏は貧しい経済状況の要因を労働者階級の人々の個人の道徳的欠如に求めたが、政治家として活動を始めると、一転して貿易保護主義を提唱し、移民が賃金を低下させ、住宅価格を上昇させていると主張するようになった。2024年にトランプ政権の副大統領に就任すると、移民が犯罪率を上昇させるというトランプ氏の主張に加え、経済的な議論も展開している。2024年の選挙で、トランプ氏は労働者階級の白人の有権者のみならず、黒人とラテン系労働者階級の有権者からの支持も獲得した。
かつては社会経済的分断が、より多くの政府プログラムを求める動きにつながったが、現在は自由貿易や気候変動、移民への反対が有権者を後押しする原動力となっている。ある意味、こうした趨勢が日米関係の緊張につながっているといえる。
(4)小尾メンバー
今年で国連気候変動枠組み条約発効(1994)から30年になり、1995年から毎年開催されている締約国会議(COP)も今年で29回目(COP29)を数えるまでになっている。30年前から気候変動の問題に国際的な取り組みがなされ、2021年に英グラスゴーで開催されたCOP26で、産業革命前と比べた地球平均気温上昇を1.5℃まで抑えることが目標として合意され、2030年までにCO₂を約45%削減(2010年比)し、2050年頃には実質ゼロにする必要があるとされた。
しかし、現時点では目標達成の見通しは立っていない。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)によると、各国がパリ協定に基づいて設定している国ごとの自主的なGHG(温室効果ガス)排出削減目標(Nationally Determined Contribution: NRD)がすべて達成されたとしても、2019―2030年の世界排出量削減は2.6%のみで、今世紀末には3℃の気温上昇につながると指摘している。日米ともに2050年までのGHG排出量ネットゼロを目標として設定しているが、実態はその軌道には乗っていない。「Climate Action Tracker」というNGOの評価指標によると、米国の取り組みはNDC指標ではほぼ十分だが、全体的には不十分という評価である。日本も2050年までのネットゼロ目標に向けての取り組みは最低の評価を受けている。
米国の国内状況と日米協力の可能性についてみると、バイデン政権は積極的な脱炭素化を推進しているが、次期トランプ政権は気候変動そのものを否定しており、石油を中心とする化石燃料の開発、及び環境保護などの規制緩和を推進している。さらに、米国では気候変動や脱炭素化が文化戦争の様相を呈しているため、政治的な協力は容易ではない。
その一方で、米国では州や都市などの地方自治体や企業など、中央政府以外のアクターが脱炭素化を推進している。また、持続可能な投資やESG投資など金融分野でも脱炭素化は重視されている。ESG投資に対する保守派からの反対キャンペーンなども見られるが、これらの中央政府とは異なる地方政府や民間アクター間での協力の可能性はある。その一つの例が、2017年に結成された、超党派の22の州知事とグアム、プエルトリコから成る「アメリカ気候同盟(the U.S. Climate Alliance)」で、パリ協定の目標達成、推進を掲げている。もう一つが、トランプ政権のパリ協定離脱に対抗する形で始まった「“America Is All In”イニシアティブ」で、パリ協定の目標遵守とそのための支援を中心とする州知事、市長、ビジネスリーダー、大学や研究機関の長などで構成される。
民間レベルでの協力も期待できる。バイデン政権下で成立したインフレ抑制法(IRA)は、約8割が気候変動対策の予算といわれている。この枠組下でEV等の産業に投資が行われているが、その投資はレッドステートに多く向けられている。そのため、IRAをなくそうという声もあるが、手続き論の問題だけでなく、実態として共和党が強い州ですでに多くの投資計画が行われており、これをゼロにするのは非常に難しいと言われている。企業の取り組みとしては「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」という国際枠組みがあり、現在は「国際会計基準(IFRS)」に引き継がれているが、日米とも企業が多く参加している。こういったところから協力関係を深める可能性も模索できるだろう。
【質疑応答】
Q1. 第二期トランプ政権における日米協力の行方
A1. 実に予測不可能である。トランプ政権の不透明性は、同盟国である日本にとっては大変な状況であるが、日本は巣瀬にトランプ政権を一度経験しているため、準備が可能である。第二期トランプ政権に対し、日本は中国に対抗できる、信頼できる同盟国であり、米国に大きく貢献できるというメッセージを研ぎ澄ますことで、不確実性をマネージすることができよう(セーチェーニメンバー)。
Q2. トランプ氏の3期目と権威主義国家になる可能性
A2. トランプ氏の3期目の実現には憲法改正が必要だが、そのための3分の2の議席を共和党が上院で獲得していないため、懸念はしていない(スラシックメンバー)。
今回の選挙戦では国民が民主主義よりインフレの改善を求めた。権力の均衡や民主主義を最重視する意識がだんだん薄れているというのが民主主義の観点からは大変懸念される状況である(三牧メンバー)。
トランプ氏の勢いは政権発足後、選挙中に比べて削がれていくと考えられるため、権威主義的なシナリオは起こらないだろう(セーチェーニメンバー)。
Q3. アジア版NATOが実現した場合の日米関係への影響
A3. 日本は近隣国を守るという条約上の制約があるため、アジア版NATOの実現は難しいが、この構想には近隣国との親密な安全保障協力、抑止強化という本質がある。むしろ「アジア版NATO」というフレーズよりも、この構想の提案が、安全保障協力にどのような影響があるかに注目している(セーチェーニメンバー)。
Q4. トランプ政権の対欧州と対アジアの姿勢の違いの背景
A4. 欧州がトランプ氏を声高に批判し、摩擦を起こしている一方で、日本を含むアジア諸国は米国への依存から表立った批判をしていない。このことは日本にも戦略的な意味合いがある。堅牢な日米の関係の構築のみならず、バイデン政権下で構築された大西洋間関係の継続にも注力しなければならない(セーチェーニメンバー)。
(文責、在研究本部)
