メモ
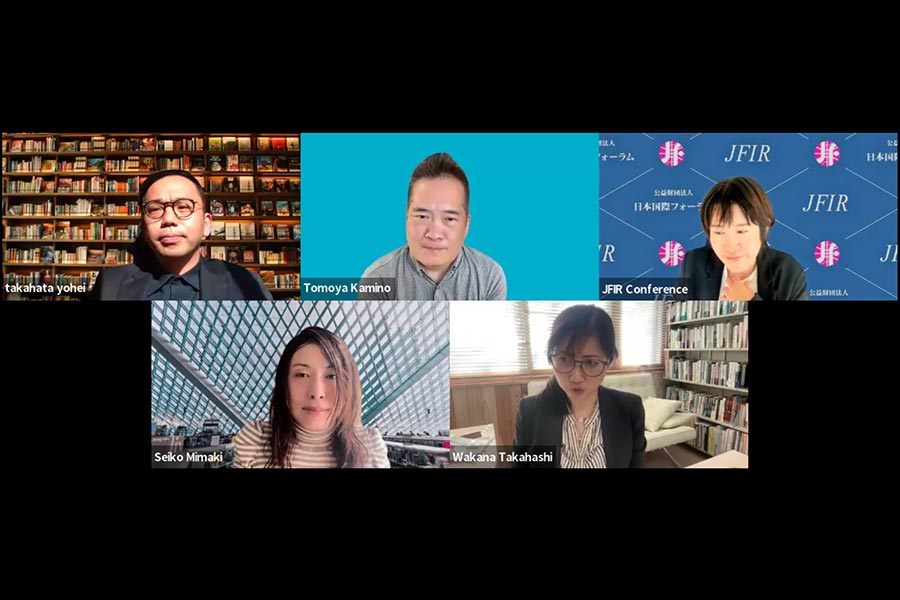
- 日 時:2025年11月17日(月)午前11時~正午
- 形 式:ZOOMによるオンライン会合
- 出席者:27名
| [報 告 者] | 三牧 聖子 | 同志社大学教授/本研究会メンバー |
| [主 査] | 髙橋 若菜 | 日本国際フォーラム上席研究員/宇都宮大学教授 |
| [副 査] | 廣瀬 陽子 | 日本国際フォーラム上席研究員/慶應義塾大学教授 |
| [事業統括] | 高畑 洋平 | 日本国際フォーラム上席研究員/慶應義塾大学 SFC 研究所上席所員 |
| [事業副統括] | 伊藤和歌子 | 日本国際フォーラム研究主幹・常務理事 |
| [メンバー] | 甲斐田きよみ | 文京学院大学准教授 |
| 上野 友也 | 岐阜大学准教授 | |
| (メンバー五十音順) | ||
| [JFIR] | 渡辺 まゆ | 理事長 |
| 大槻 歩未 | 研究助手 他18名 |
- 議論の概要

(1)三牧メンバーによる基調報告「『ホワイト・フェミニズム』を超えて:『フェミニスト外交』の批判的検討」
フェミニスト外交(Feminist Foreign Policy: FFP)は、2014年にスウェーデンのマーゴット・ヴァルストローム外相によって初めて明確に掲げられた政策理念である。外交のあらゆる領域でジェンダー平等を推進することを目的とし、ヴァルストロームは自身が国連事務総長特別代表(2010〜2012)として紛争下の性的暴力問題に取り組んだ経験を踏まえ、女性や少女のニーズが国際援助で軽視されてきた現実への危機意識を明示した。その上で、FFPの基軸として「権利(Rights)」「代表(Representation)」「資源(Resources)」のいわゆる3Rを提示し、①女性・マイノリティの権利保護、②意思決定過程への参画、③政策資源の公正な配分を外交の組織原理として位置づけた。
しかし、この理念は必ずしも一貫して実践されてきたわけではない。象徴的なのが、スウェーデンによるサウジアラビアへの武器輸出である。ヴァルストロームが同国の人権状況を批判し輸出停止を表明したにもかかわらず、実際には取引が継続されたことは、FFPと現実政治の乖離を如実に示した。また2022年には新政権が「フェミニスト外交」という名称そのものが誤解を招くとして使用を中止し、人権団体からは後退を懸念する声も上がった。FFPは導入からわずか10年足らずの間に、政治的環境や保守的反発の影響を強く受ける不安定な政策枠組みであることが明らかになった。
一方、FFPの歴史を振り返る際には、欧米が果たして理念どおりの旗振り役だったのかという根本的問いも避けられない。アメリカでは長年、女性の権利や解放の言説が軍事介入の正当化に利用されてきた。2001年の同時多発テロ後、キャロライン・マロニー下院議員はブルカをまとい「声をあげられないアフガン女性を解放すべきだ」と主張し、複数のフェミニスト団体も軍事介入を支持した。ローラ・ブッシュ元大統領夫人は「米国が女性を解放した」と強調したが、その恩恵を受けた例は都市部の限られた層にとどまった。ラフィア・ザカリアがこの戦争を「最初のフェミニスト戦争」と呼んだように、女性の権利が戦争支持の言説資源として機能した点は批判的に評価されるべきである。
同様の構図は現在の中東情勢にも見て取れる。ドイツのアナレーナ・ベアボック外相は2023年に「フェミニスト外交政策指針」を発表したが、ロシアによるウクライナ侵攻を民間人保護の観点から厳しく批判する一方、イスラエルへの軍事支援には積極姿勢を示した。米国でも、シェリル・サンドバーグやヒラリー・クリントンなど著名なフェミニストがハマスによる性暴力には強い批判を向けつつ、パレスチナ女性や民間人への暴力については言及が乏しかった。「性暴力という絶対悪は許すな」という言説が、苛烈な軍事行動の正当化に用いられるという、構造的な問題がここにも表れている。こうした事例は、「欧米フェミニズムは中東を視野に入れていない」とする非西洋メディアからの批判を招いている。
以上のように、欧米主導で展開されてきたフェミニスト外交は、普遍的な理念を掲げながらも、実際には選択的適用や政治的利用を免れず、非西洋世界の女性を「保護されるべき対象」として描くまなざしには、依然としてポスト植民地主義的な構図が温存されている。
日本は、地理的にも歴史的にも「西洋」と「グローバルサウス」の中間に位置し、いわば両者を橋渡しする潜在的役割を担いうる立場にある。日本のWPSやフェミニスト外交の実践は、アジア諸国やグローバルサウスとの協働を通じて、欧米中心の「ホワイト・フェミニズム」を超えた、より普遍的かつ当事者の声を反映したフェミニズム外交の構築に寄与しうるのではないか。こうした経緯をふまえ、今後我々は日本外交が持つ可能性と課題について真剣に考えなければならない。
(2)自由討論
(a)髙橋主査:バックラッシュと日本の役割について
Q1. 2022年のスウェーデン滞在で、環境政策でもバックラッシュが強まっていると実感した。ホワイト・フェミニズムの下で「守るべき対象の選別」が進む状況において、日本はどのような役割を果たし得るのか。
A. 欧米や韓国などでジェンダー政策への反発が激しくなる一方、スウェーデンでは保守政権下でもジェンダー政策が一定維持されている点は評価できる。日本におけるWPS研究の継続自体が、バックラッシュの時代を耐えるための基盤づくりとなり得る。
Q2.「守る対象の選別」という構造は、どのレベルで最も強固に現れているのか。
A. アメリカでは長らく親イスラエルの立場から選別が行われてきた。しかし近年では、パレスチナ国家承認に賛成する世論が反対を上回るなど、ホワイト・フェミニズム自体に修正の兆しが見られる。本質主義的に捉えるのではなく、変化し得るものとして理解する必要がある。
Q3. ホワイト・フェミニズムへの批判が、フェミニズムそのものの否定と混同されないようにするにはどうすべきか。
A. 非常に難しい問題である。アフガニスタン侵攻を支持したフェミニスト・マジョリティ財団は、米国内で中絶の権利などに実績がある一方、アフガニスタン侵攻については20年経った今も「女性を解放した戦争」と正当化し続けている。こうした団体を弁護するのではなく、批判的検討を通じてフェミニズムを「未完のプロジェクト」として高めていく姿勢が重要である。
(b). 高畑統括:日本外交の可能性と政策効果の評価について
Q. 日本が「仲介的立場」で貢献するとすれば、どのような外交措置や知的インフラが必要か。また、理念先行のFFPやWPSの政策効果を評価する際には何を重視すべきか。
A. 現状、日本はイスラエル問題を含め立ち位置が定まっていない。普遍的・中立的立場からの人道支援を軸に、欧米とは異なるWPSの理念形成に貢献する余地がある。また政策効果を測る際には、「理念の提示」ではなく、具体的な行動や制度設計の変化に注目すべきである。
(c). 伊藤副統括:アジア太平洋地域での展開について
Q. 東南アジアや太平洋諸国にフェミニズムを広げるにあたり、家族観・宗教観などの違いを踏まえる必要がある。日本の役割は何か。
A. 日本は欧米よりもアジアや太平洋諸国と価値観を共有しやすい側面がある。その共通性を生かし、欧米式フェミニズムの単純な「輸入」ではなく、地域に適合的なWPSやフェミニズムのモデルを協働で設計していく視点は極めて重要である。
(c). 上野メンバー:フェミニズムと言説資源としての国際政治
Q. アメリカが軍事介入の正当化根拠としてフェミニズムを使うようになったのは2000年代以降である。これは逆に、フェミニズム言説自体が国際政治で一定の力を持つようになった証左ではないか。また、日本の役割は何か。
A. 確かに、フェミニズム言説が国際政治で影響力を持ち始めたことは事実だが、対テロや安全保障上の要因と比較してどの程度の重みがあったかは慎重に検討する必要がある。日本には、米国が撤退しつつある人道支援分野を補完し、維持する役割が期待される。
(コメント)髙橋主査:
日本は欧米モデルの単なる踏襲ではなく、アジア諸国との協働を通じて新たな「アジア型フェミニズム/WPSモデル」を構築すべきである。
(以上、文責在研究本部)